
課題は理想から始まる
こんにちは。KiKiKiです。
大学生の時に舞台衣装の仕事を始めてから、デザイナーをやったり、エンジニアをやったり、スタートアップでPdMをやったり、起業してみたり、ふらふらしながら生きています。
抽象化したりメタ認知的な事を考えるが好きなので今回は「課題」とゎ何かを考えてみたいと思います。
課題とゎ?
「課題解決」新しい事業やサービスを始める時によく言われる言葉です。
お金を払ってでも解決したいと思っている偏頭痛級の課題を見つけよう。企業の本でもよく聞く言葉です。裏を返せば「課題」さえ見つけられれば、市場規模規模など他の問題はさておき一定の需要を見つけ出すことができます。
では課題とは何なのでしょう? 課題とは何か、どうすると人は課題を認識するのか。
これを抽象化できるとビジネスの種を見つけるのが容易になりそうです。
先進国に大きな課題は残っていない?
電気も水道もまばらで、一般的な家庭には電気の通ってない地域も多くあり、就学率もあまりよくはなく、治安も…
そんな色々な物事が不足している環境であれば課題はそこら中に山積しているでしょう。
一方この記事の多くの読者の暮らす日本はどうでしょうか?
裕福までとは言えなくとも電気水道ガスは揃っており、地方であっても24時間営業しているようなコンビニがあり、病院の仕組みや下水などの衛生面もよく治安も悪くない。多くの人が小さな不満がありつつもそれなりに暮らせいる…そんな社会なのではないでしょうか。
仕事でFAXを使っていても、お店の予約が電話だけだとしても少し面倒だなと思いつつも死ぬほど困っているわけではない。そんな感じの社会ではないかと思います。
つまり、後継者不足・年金問題など人口減少に紐づく課題が今後出てくる事は予見されますが、死ぬほど困っているという片頭痛級の大きな題というのは殆ど残ってないのではないでしょうか?
大きな課題はそう残っていないのではないか?
世界を変えるぜ!と息巻くスタートアップを目指す方にはがっかりする言葉かもしれません。しかし、この「大きな課題はないが、誰しもが小さな不満を抱えつつもまぁ何とかなっている」という状況は、セグメントを絞った代替サービスを提案するスモールビジネスには寧ろチャンスであるように思います。
と言いつつも、何とかなっている人たちは何とかなっているから現状を変える事には消極的でしょう。
今何とかなっているのにリスクを犯して、慣れているやり方を変えてまで新しい方法を取り入れる必要があるのか? 食べ物が無くなっても食べ物があるかわからない隣の山に移動するのではなく、食べ物が増えるのを待つ動物が多いように、人間もまた基本的には保守的な生き物なのです。
「何とかなっている」という状況は彼らにとって、それを大きな課題として認識していない状態です。では、どうすれば解決したい課題として認識してもらえるのでしょう?
比べるからこそ欲が生まれる
例えば携帯電話の存在しない世界に暮らしていたとします。
人々は固定電話しか知りませんから、電話をするには固定電話のある所に行くのが当たり前だと認識しています。その世界の人々は当たり前の事なので少しの面倒さを感じつつも、大きな不満は持ってないでしょう。
私達がそれを不便だと感じられるのは持ち運びができる携帯電話を知っているからで、インターネットにも接続できるスマートフォンを知っているからに他なりません。
つまり、心のなかで固定電話とスマートフォンと比べて固定電話は不便と判断しているのです。スマートフォンを知っているあなたの不満は、固定電話しか知らない国の人の不満より遥かに大きいはずです。
幸福度調査で幸福度が高かったある国を調査したら、その国は情報統制が徹底されていて、人々は自分たちの暮らし以外の生活が存在していることを知らなかった。といったデータもあります。子どもが友達が持っているものと同じものを欲しがるのも、友達と比べて自分が持っていないという不足の差を認識したからでしょう。
つまり、より良いモノ・方法に出会うことで課題感は大きくなるのです。
課題とは理想との差
言い換えれば、「課題とは理想の状態との差」です。
より良い状態を認識することで、現状を課題だと感じるようになります。

現実と理想の差が課題となる。差が大きくなるほど課題感が増す
広くユーザーを集めているサービスなどでは特定の分野・ドメインに於いては少し不便だけど替えが無い/知らないから使い続けているというケースも多いでしょう。
既にあるビジネスから特定の小さなパイを奪うようなスモールビジネスの場合は、自分の知っている分野やドメインであればその少しの不便を改善した理想の状態を思い描きやすいのではないでしょうか?
まずは理想を掲げることから始めよう
理想の状態を提示することで、ユーザーの現状が課題のある状態だと認識させることができる。
抽象化するとこんな感じでしょうか。
自分の知っている分野・ドメインであれば、理想の状態を説明するのも比較的容易でしょう。
まずは、自身が身をおいている分野での小さな不満や不便を見つけること。どんな状態だと理想的かを思い描くことからスモールビジネスへの一歩を踏み出してみるのが良いのではないでしょうか。
(有料部分には特に何もありません。)
おすすめ記事
店舗M&Aはこう攻めろ!買収1年で利益率50%を達成した舞台裏
 Biz library編集部
¥1,980
2025.11.10
Biz library編集部
¥1,980
2025.11.10
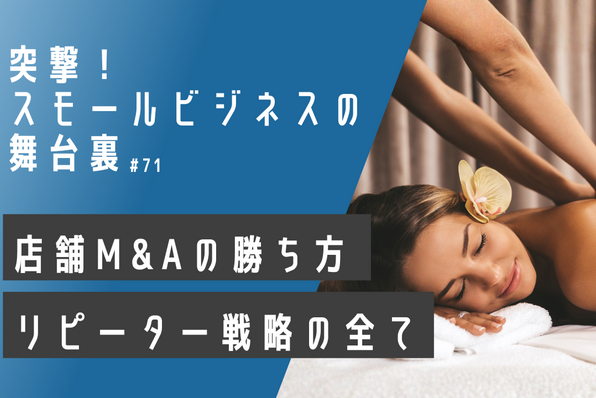
売上1.7億円、社員数30名のシステム開発支援と受託開発事業を作り上げたスモビジマン
 Biz library編集部
¥1,980
2025.7.24
Biz library編集部
¥1,980
2025.7.24
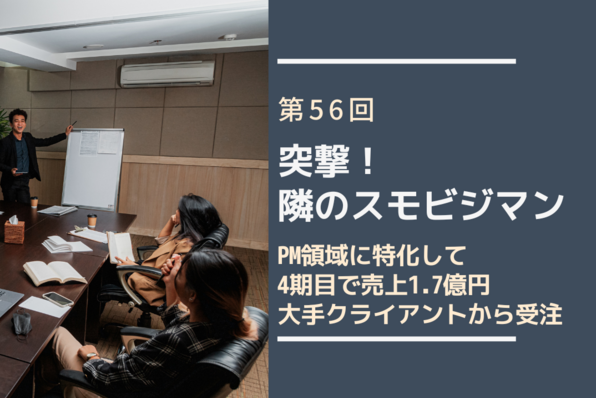
「楽勝だ」は勘違いだった。物販ECの理想と現実、失敗から学ぶ経営
 Biz library編集部
¥1,980
2025.9.25
Biz library編集部
¥1,980
2025.9.25
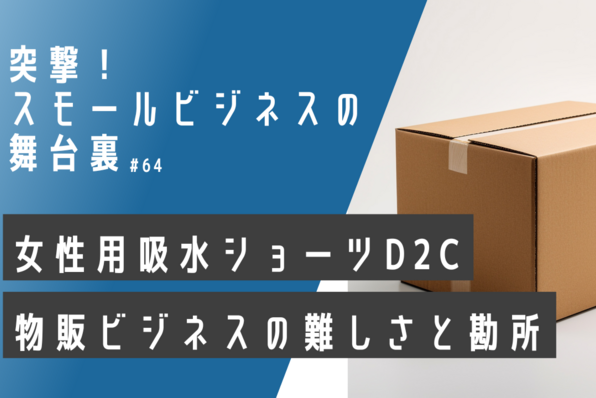
3年目で年商数十億!海外で見つけた生活消費財ブランドを国内で販売するスモビジ
 Biz library編集部
¥2,480
2023.3.9
Biz library編集部
¥2,480
2023.3.9

【会員限定】武田のスモビジ奮闘日記 スモビジオーナーの書籍出版の苦労とリターンについて語ってみた【vol9】
 Biz library編集部
会員限定
2024.4.1
Biz library編集部
会員限定
2024.4.1

【会員限定】武田のスモビジ奮闘日記 スモビジ初心者のためのM&A入門【vol.17】
 Biz library編集部
会員限定
2024.9.17
Biz library編集部
会員限定
2024.9.17

【出版記念】12月 オンラインイベント詳細【オープン&クローズそれぞれ開催】
 Biz library編集部
無料
2023.12.4
Biz library編集部
無料
2023.12.4

M&Aを目指すなら読みなさい!属人性の高い事業を営むスモビジマンに贈るM&A虎の巻
 Biz library編集部
¥1,980
2025.6.11
Biz library編集部
¥1,980
2025.6.11

月商700万、コンサル特化のBtoB営業代行!営業最強企業で学んだ営業の極意
 Biz library編集部
¥1,980
2024.12.28
Biz library編集部
¥1,980
2024.12.28

年商3億、利益1億超!トレーディングカード業界でヒット商品を連発するスモビジマン
 Biz library編集部
¥1,980
2024.5.22
Biz library編集部
¥1,980
2024.5.22

こんにちは。KiKiKiです。
大学生の時に舞台衣装の仕事を始めてから、デザイナーをやったり、エンジニアをやったり、スタートアップでPdMをやったり、起業してみたり、ふらふらしながら生きています。
抽象化したりメタ認知的な事を考えるが好きなので今回は「課題」とゎ何かを考えてみたいと思います。
大学生の時に舞台衣装の仕事を始めてから、デザイナーをやったり、エンジニアをやったり、スタートアップでPdMをやったり、起業してみたり、ふらふらしながら生きています。
抽象化したりメタ認知的な事を考えるが好きなので今回は「課題」とゎ何かを考えてみたいと思います。
課題とゎ?
「課題解決」新しい事業やサービスを始める時によく言われる言葉です。
お金を払ってでも解決したいと思っている偏頭痛級の課題を見つけよう。企業の本でもよく聞く言葉です。裏を返せば「課題」さえ見つけられれば、市場規模規模など他の問題はさておき一定の需要を見つけ出すことができます。
では課題とは何なのでしょう? 課題とは何か、どうすると人は課題を認識するのか。
これを抽象化できるとビジネスの種を見つけるのが容易になりそうです。
先進国に大きな課題は残っていない?
電気も水道もまばらで、一般的な家庭には電気の通ってない地域も多くあり、就学率もあまりよくはなく、治安も…
そんな色々な物事が不足している環境であれば課題はそこら中に山積しているでしょう。
一方この記事の多くの読者の暮らす日本はどうでしょうか?
裕福までとは言えなくとも電気水道ガスは揃っており、地方であっても24時間営業しているようなコンビニがあり、病院の仕組みや下水などの衛生面もよく治安も悪くない。多くの人が小さな不満がありつつもそれなりに暮らせいる…そんな社会なのではないでしょうか。
仕事でFAXを使っていても、お店の予約が電話だけだとしても少し面倒だなと思いつつも死ぬほど困っているわけではない。そんな感じの社会ではないかと思います。
つまり、後継者不足・年金問題など人口減少に紐づく課題が今後出てくる事は予見されますが、死ぬほど困っているという片頭痛級の大きな題というのは殆ど残ってないのではないでしょうか?
大きな課題はそう残っていないのではないか?
世界を変えるぜ!と息巻くスタートアップを目指す方にはがっかりする言葉かもしれません。しかし、この「大きな課題はないが、誰しもが小さな不満を抱えつつもまぁ何とかなっている」という状況は、セグメントを絞った代替サービスを提案するスモールビジネスには寧ろチャンスであるように思います。
と言いつつも、何とかなっている人たちは何とかなっているから現状を変える事には消極的でしょう。
今何とかなっているのにリスクを犯して、慣れているやり方を変えてまで新しい方法を取り入れる必要があるのか? 食べ物が無くなっても食べ物があるかわからない隣の山に移動するのではなく、食べ物が増えるのを待つ動物が多いように、人間もまた基本的には保守的な生き物なのです。
「何とかなっている」という状況は彼らにとって、それを大きな課題として認識していない状態です。では、どうすれば解決したい課題として認識してもらえるのでしょう?
比べるからこそ欲が生まれる
例えば携帯電話の存在しない世界に暮らしていたとします。
人々は固定電話しか知りませんから、電話をするには固定電話のある所に行くのが当たり前だと認識しています。その世界の人々は当たり前の事なので少しの面倒さを感じつつも、大きな不満は持ってないでしょう。
私達がそれを不便だと感じられるのは持ち運びができる携帯電話を知っているからで、インターネットにも接続できるスマートフォンを知っているからに他なりません。
つまり、心のなかで固定電話とスマートフォンと比べて固定電話は不便と判断しているのです。スマートフォンを知っているあなたの不満は、固定電話しか知らない国の人の不満より遥かに大きいはずです。
幸福度調査で幸福度が高かったある国を調査したら、その国は情報統制が徹底されていて、人々は自分たちの暮らし以外の生活が存在していることを知らなかった。といったデータもあります。子どもが友達が持っているものと同じものを欲しがるのも、友達と比べて自分が持っていないという不足の差を認識したからでしょう。
つまり、より良いモノ・方法に出会うことで課題感は大きくなるのです。
課題とは理想との差
言い換えれば、「課題とは理想の状態との差」です。
より良い状態を認識することで、現状を課題だと感じるようになります。

広くユーザーを集めているサービスなどでは特定の分野・ドメインに於いては少し不便だけど替えが無い/知らないから使い続けているというケースも多いでしょう。
既にあるビジネスから特定の小さなパイを奪うようなスモールビジネスの場合は、自分の知っている分野やドメインであればその少しの不便を改善した理想の状態を思い描きやすいのではないでしょうか?
まずは理想を掲げることから始めよう
理想の状態を提示することで、ユーザーの現状が課題のある状態だと認識させることができる。
抽象化するとこんな感じでしょうか。
自分の知っている分野・ドメインであれば、理想の状態を説明するのも比較的容易でしょう。
まずは、自身が身をおいている分野での小さな不満や不便を見つけること。どんな状態だと理想的かを思い描くことからスモールビジネスへの一歩を踏み出してみるのが良いのではないでしょうか。
(有料部分には特に何もありません。)
店舗M&Aはこう攻めろ!買収1年で利益率50%を達成した舞台裏
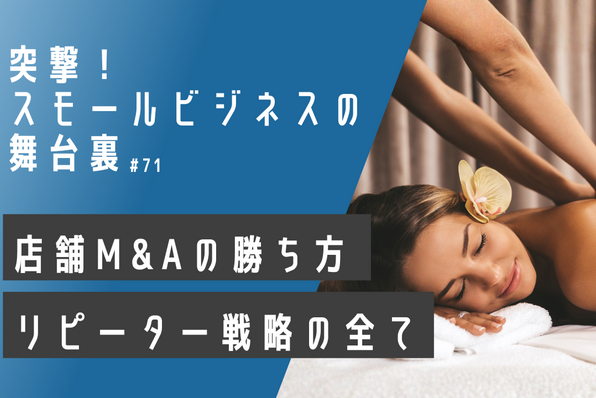
売上1.7億円、社員数30名のシステム開発支援と受託開発事業を作り上げたスモビジマン
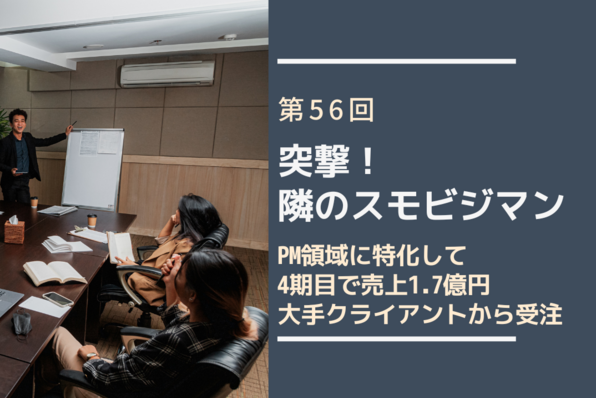
「楽勝だ」は勘違いだった。物販ECの理想と現実、失敗から学ぶ経営
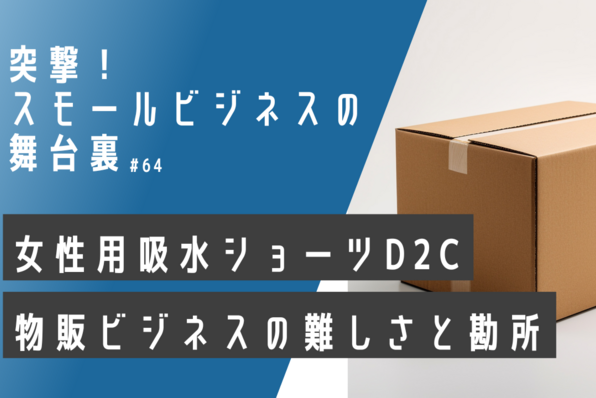
3年目で年商数十億!海外で見つけた生活消費財ブランドを国内で販売するスモビジ

【会員限定】武田のスモビジ奮闘日記 スモビジオーナーの書籍出版の苦労とリターンについて語ってみた【vol9】

【会員限定】武田のスモビジ奮闘日記 スモビジ初心者のためのM&A入門【vol.17】

【出版記念】12月 オンラインイベント詳細【オープン&クローズそれぞれ開催】

M&Aを目指すなら読みなさい!属人性の高い事業を営むスモビジマンに贈るM&A虎の巻

月商700万、コンサル特化のBtoB営業代行!営業最強企業で学んだ営業の極意

年商3億、利益1億超!トレーディングカード業界でヒット商品を連発するスモビジマン

